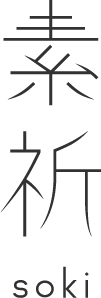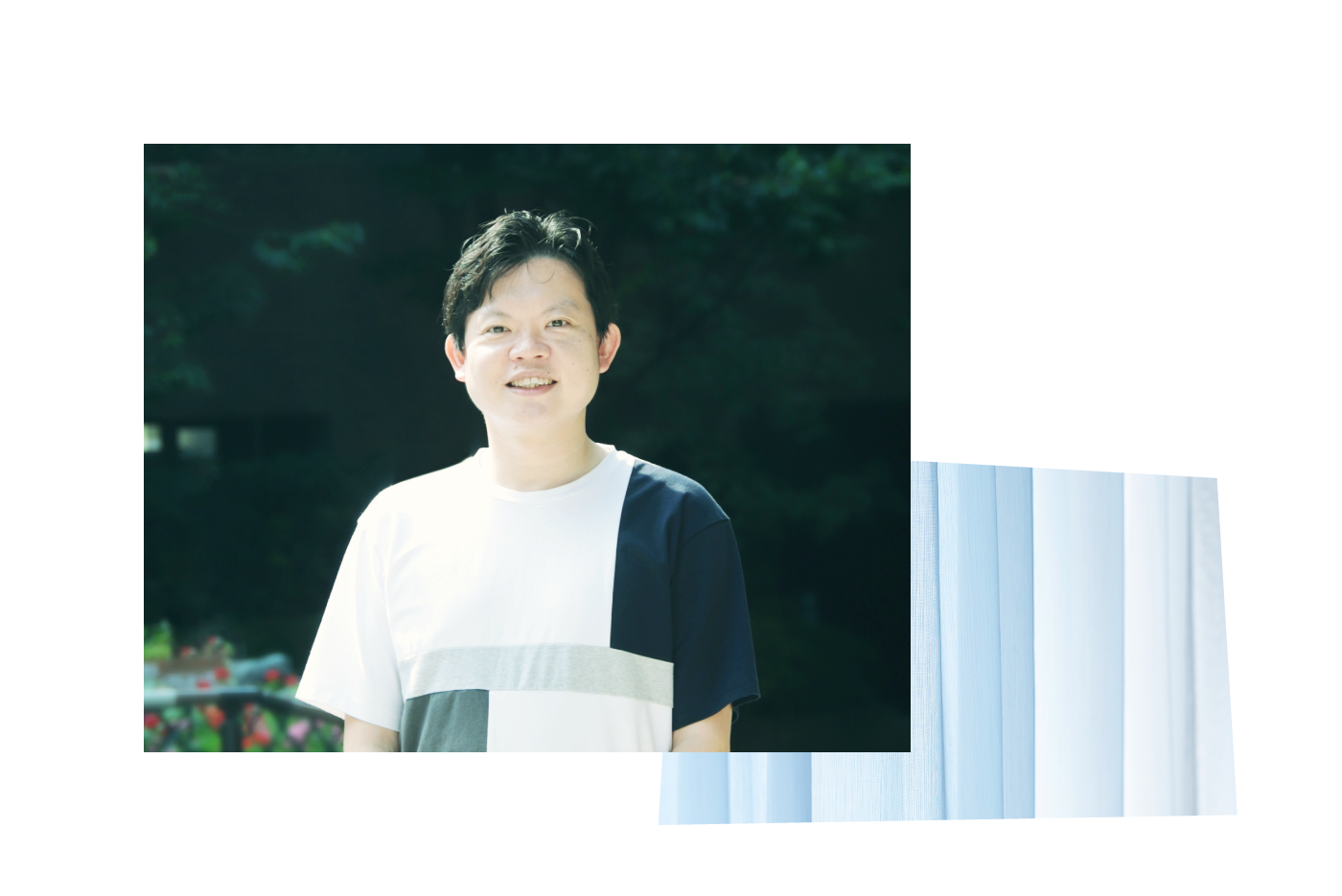
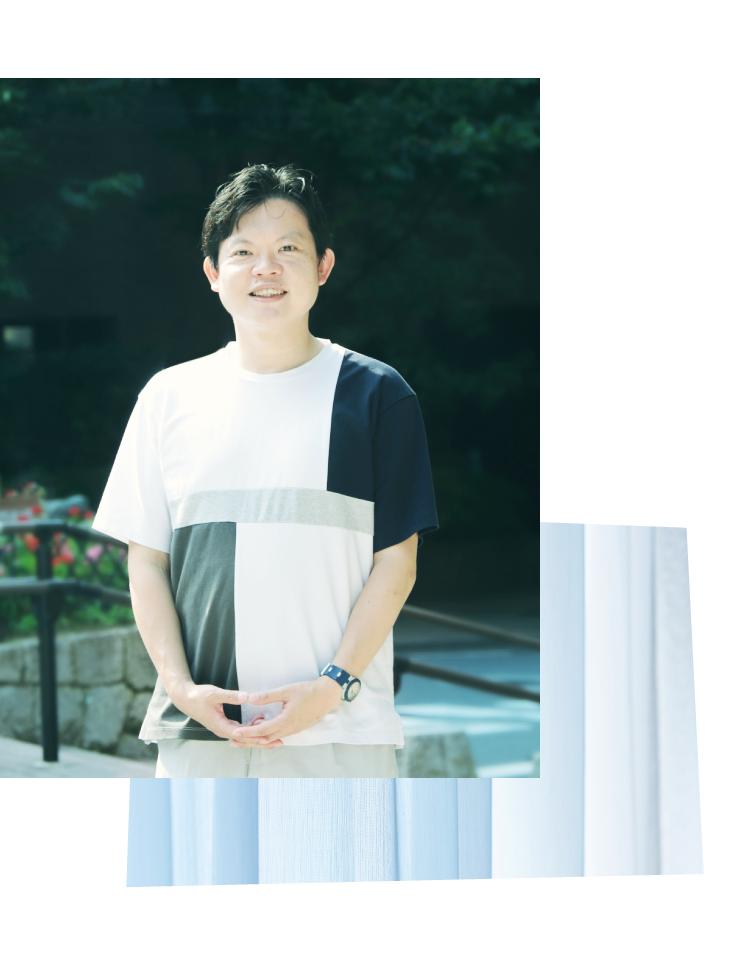
偲ぶとともに生きる
アイデンティティをつなぐこと
Essential
2022.8.19 Text:Yuriko Hayashi
大切な人を想い、偲び続ける人がいる。その姿と心から、様々なご供養のかたちやご供養のある日々がもたらすことを学び、未来へ繋ぐインタビュー連載。
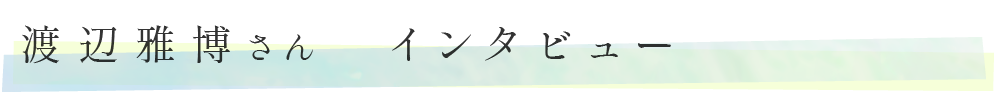
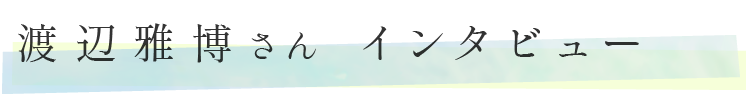
郷里を離れ、都内に構えた自宅マンションで家族4人暮らしの雅博さんは、39歳で母とのお別れを迎えた。人生の節目となる親の死をどのように受け入れ、ご供養を紡いでいるのか? 夏のある週末、インタビューの席についた雅博さんの口からは、溢れる想いが語られた。


ショックを受ける子供の姿に、何よりも胸が痛んだ
三重県で離れて暮らしていた雅博さんの母親、博美さんが亡くなったのは2021年の初頭。持病が再発し、手術を受けた後のことだった。
術後に目覚めた博美さんと言葉を交わし、翌朝、雅博さんが東京へ戻ろうとした矢先に容態が急変。合併症によってひと月後に息を引き取り、最期を見届けることは叶わなかった。雅博さんは「家族で駆けつけ、母の亡骸と子供たちを対面させた瞬間は人生で一番辛い場面でした。ばぁばに買ってもらったピンク色の服を着て泣きじゃくる娘の姿を思い出すと、今も胸が痛みます」と当時を振り返る。
お別れから約1年半。悲嘆にくれるわけではないが、毎日ふと母のことが胸をよぎる。「自分が死ぬまでこういう想いはずっと続くのかもしれないですね。母はもういないという寂しさ、ばぁばを早くに亡くした子供たちが可哀相だという気持ち。このふたつは最初から変わらないんです」。




死を悟っていたかのように、全うした母の生き方
思い返すと、博美さんは手術のたびに必ず「貴重品や暗証番号はまとめてある」と雅博さんへ伝えていた。また、最後の入院前には自ら年金事務所へ出向き、受給を前倒しにする手続きを行っていた。さらに、亡くなった後の遺品整理中には、大切にしていたバッグの中からへその緒が発見される。バッグには母の字で「雅博へ」と記したネームタグが添えられていた。
死を察していたかのような行いの背景にあったのは、若くして倒れ、持病があったからこその死生観だろうか。生前の博美さんは、息子が「なぜそんなに」というほど仕事に打ち込み、休暇にはいいホテルに泊まって優雅に過ごすのがルーティーン。後から知ったことだが、同僚には「歩けるうちに色んなところへ行く」と話していたそうだ。いつ何かあってもいいよう、やり残すことのないよう、そんな覚悟が垣間見える。
「もう少し本音で話しをしておけばよかったと思う反面、母には母の世界があり、母と息子ふたりの関係で踏み込めない部分があるのは仕方がなかったようにも感じます。でも、孫にも慕われ、わずか数ヶ月分とはいえ年金を受け取れる年齢まで生きて、まだ65歳と若かったけれど人生を全うしたのだと思わせてくれました」。


お位牌は、故人の象徴や想い出させるスイッチのようなもの
「亡くなってしばらくは遺品整理で頭が一杯で、妻から言われるまで位牌のことはノーアイデアでした」。当時、妻である佑実子さんの父親は長らく病の床についており、佑実子さんの頭には「いずれ自分が受け継ぐ家族の位牌は、私自身が供養しやすいものを」という考えがあったそう。色々と探す中で【まなか】に興味を持っており、雅博さんに紹介した。
一方、両親が離婚している雅博さんには、引き継ぐべき先祖代々のお仏壇やお墓がない。お位牌について、雅博さんは「残された人間の気持ちの問題だと思うので、言葉を選ばずに言うなら、なくてもよかったのかもしれません。慣習として作るのであれば、一律の機能を備えた上で、母らしさを感じられるものがよかった」と言う。
家族がすごすリビングの一角。遺影や愛用品、子供たちの絵手紙などを置いた“ばぁばコーナー”の真ん中に、ジュエリーを飾るような感覚で【まなか】のお位牌をしつらえ、お線香の代わりに添えるのは、博美さんが好きだったホテルの香り。
優しいイメージをたたえるピンク色のお位牌を選んだのは、お嬢さん。亡くなってからというもの「ばぁばは私の側にいるんだよ」と、しばしば博美さんを代弁するような言動を見せるのだとか。
“ばぁばコーナー”へ、家族が手を合わせることはない。雅博さんは、祈るまでもなく日々母のことを思い出す。博美さんの魂があるのなら、お位牌やお骨に宿るのではなく、子供たちの近くに寄り添っている。家族にとってお位牌はあくまで「ひとつのシンボル、故人を想起するスイッチ」なのだ。





思い出が子供たちのアイデンティティになることを願って
「雅博さんにとって、お母さまを偲ぶこととは?」。
問いかけに対し、少し間を置いて返ってきたのは「娘と息子にばぁばを忘れないでいてもらうために、何ができるかを考えることかもしれないですね」という答え。
というのも、幼い頃に両親が離婚した雅博さんは、自分をどこかずっと根無し草のように感じていたのだそう。今回、実家を引き払って東京に新しく母のお墓を設けることになった時、いよいよ自分のルーツが消えてしまう不安を感じた。
だが、博美さんの関係者へ訃報を届ける過程で、さまざまな発見があった。また、諸手続きのために戸籍を取り、じっくり眺める機会も得た。豊かな交友関係、大学時代にがんばっていたこと、知らなかった苦労話など、改めて母や祖父母の人生を辿ることになった雅博さん。「死後に母から色んなメッセージを受け取った気がして。そうか……、って」。伏せた眼差しに、亡くならなければ知りえなかったことも受け止めようとする、偲ぶ姿が見えた。
「でも、改めて自分のルーツを知ることができて本当によかった。これもひとつの供養ですよね」。と、雅博さんは視線を上げる。
「娘と息子には、自分たちのルーツを知り、揺るぎないアイデンティティを持って生きてもらいたいんです」。そう願う雅博さんは、時々子ども達と博美さんの写真や動画を開き、折に触れて家族でゆかりの地を旅する。子どもたちの成長に合わせてひとつ、またひとつと亡き母のエピソードを伝えていくつもりだ。




お母さまが亡くなった後も、新しい思い出が増えていく。
そのことをひとつのご供養と捉える豊かさは、お母さまがいない寂しさと向き合う真摯な心が生み出したのだろう。
お母さまを想うことは、次の世代へ、さらには未来へ、つながっていく。
今はまだ、お母さまのゆかしい愛情の痕跡がノスタルジーを運ぶ。
しかし、お母さまを想い、寂しさと向き合う雅博さんの未来には、今までとは違う深度の発想や発見が満ちていくことと思う。
大切な人を想うことは、ご供養にとって一番大切なことではないだろうか。
それが慣習による行為ではなく、日常におのずとあるのであれば尚のこと。
これからを生きるための祈りの道具を提案する【祈りの道具屋 まなか】のお客さまは、
まなかの想像以上に、ご自分らしい祈りのかたちを築いていた。
今を生きるリアルは、東京の真ん中で祈りの未来を体現している。
うつろう時代に、祈ることの真価はこの先も問われ続けるだろう。
最後に、貴重なお話を聞かせてくださった渡辺 雅博さまに深く感謝いたします。
これからも日々を紡ぎ、揺るぎない未来が続いていくことを心より願っています。