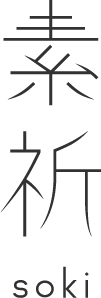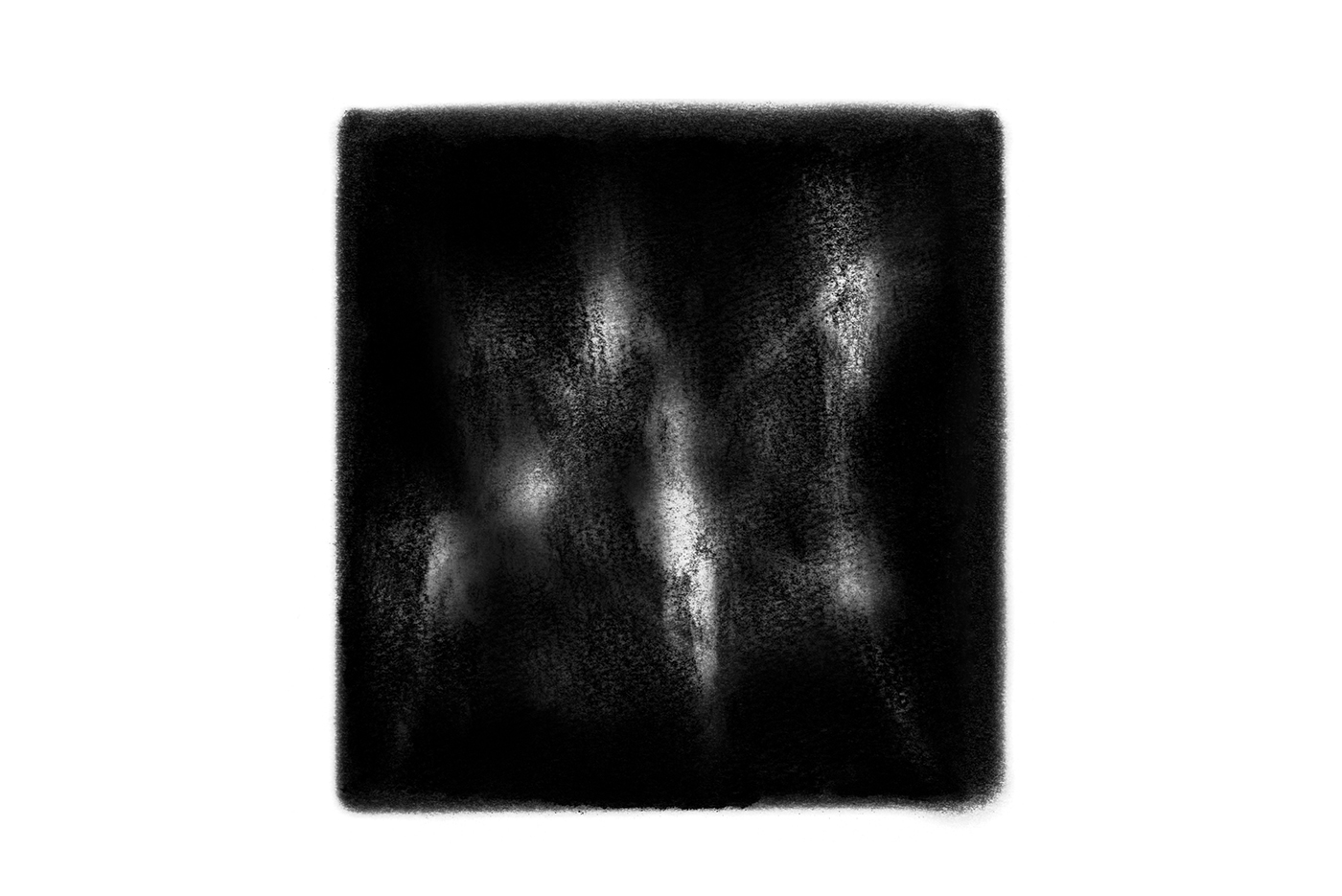
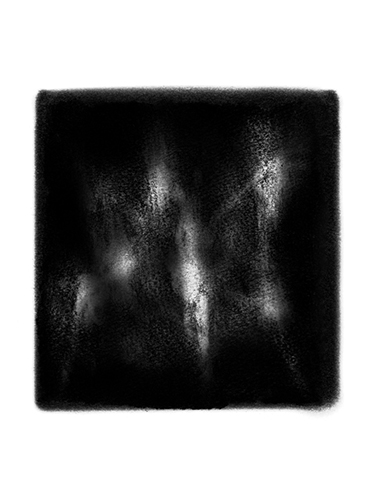
偲ぶことを考える
現実の身体に芽生えた感情の力
Essay
2022.12.2 Illustration:Makoto Motomura
古来より人は、死者を弔い偲んできた。それは国境問わず、それぞれの風土や民度をベースとし、様々な手法で定着し受け継がれている。なぜ人は、偲ぶのだろうか。なぜ人は、死者を想うのだろうか。今連載では、そんな人類独自の根源的な営みを、様々な実例や解釈を元に紐解いていきたい。
生と死を考える。
考えると書くと、
机でうんうんと唸りながら、
論理的な思考のみで
推し進めていくということを
想像してしまいがちだが、
おそらくそれは限りがあって、
実は人が現実に
この身体ごと晒しながら
芽生えた感情の力が、
考えることなのだと思う。
小説家・保坂和志の
「生きる歓び」(1999年)、
「ハレルヤ」(2018年)
という小説を読むたびに、
こういった思いを巡らしてしまう。


「生きる歓び」では、
生まれつき目が不自由で、
ウィルス性の鼻風邪をこじらせ
衰弱している子猫の
”花ちゃん” を拾い、
懸命に看病する夫婦の姿が描かれ、
「ハレルヤ」では、
リンパ腫を患った ”花ちゃん” の
治療に奔走する夫婦の姿が描かれる。
二つの小説では
猫や登場するものたちが
病に翻弄される姿が
描かれているのだけれど、
それらが闘病記として
感動的なのではなく、
「言葉を持たないもの」である
”花ちゃん” と、
「心の奥の声を探り続ける」
夫婦との交わりや触れ合い、
祈りに似た日々の魂の交換に、
読んでいるわたしは
どうしても激しく心を
揺さぶられてしまう。


主人公である ”私” は
4年と4ヶ月の
短い命で死んでしまった飼い猫
“チャーちゃん” のことを
思い出す場面がある。
(…)短い命を生きることだけが
チャーちゃんのしたことで
短い命の子は言葉を残さず、
最後の呼吸で
月を見上げて鳴いたら
それっきり飛び散って、
光や風や波になる、
姿も形も動作も残さず
光や風や波になった、
祈りと同じだ。
チャーちゃんは
何も言葉を残さなかったから
私は人間としての宿命で
心の奥の声を
探り続けることになった、
それは祈りだから
そこに言葉はなかった、
光と風と波だけがあった。
保坂和志「ハレルヤ」
(新潮社 2018年)


たとえば
「言葉を持たない」ものを死者、
死者の
「心の奥の声を探り続ける」ものを
生者
として考えてみてはどうだろうか。
フランスの哲学者・アラン
(1868~1951)は
死者に関するエッセイの中で、
死者は
肉体から開放されることによって、
死者の存在は
純粋な精神となり、
うるわしい面影になる。
生者は死者のうるわしい面影だけに
再会できる、と指摘する。
二つの小説は「生」と「死」の
手触りというか感触のようなものが、
一対になって響き合い
呼応しているように見える。
わたしはこの感触を
感じたいがために、
またこの二つの小説を
繰り返し読んでしまう。