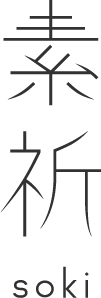会いたい人に会いに行く|塚田有那
END展キュレーター・塚田有那 (後編)
Interview
2023.5.19
WEBマガジン「素祈」を運営する株式会社まなかの代表・宮嶋が、「偲ぶことの真ん中と向き合う」をテーマに人に会いに行く本連載。「素祈=ありのままに祈ること」という習慣をもっと豊かにするために、異なる文脈から「祈り」に触れる人々と対談をしていきます。
第二回となる今回の対談相手は、2022年に東京で開催された展覧会「END展」のキュレーター・塚田有那さん。「END展」では、その展示を通してさまざまな死生観の形が表現されました。そんな場を生み出した塚田さんと、現代における「死を思うこと」についてお話ししていきます。(前中後編の後編記事となります)
脱人間中心主義に「これから」のヒントがある


塚田私は最近よく「これからの死とか弔いってなんだろうね」という話をいろいろなところでしているんです。たとえば、死って人間だけの問題ではないじゃないですか。遠野のように山深い場所に行くと、山のふもとに行くだけでシカの死骸がありますし、いろいろな命が循環していることを肌で感じるわけですよね。
前回もお話した遠野の郷土芸能であるしし踊りも、人間と同じように魂を持つシカを供養しなければならないという発想から始まった文化だったと考えると、人間中心主義で考えてきたことに限界が来ていると感じ始めました。
宮嶋「END展」でも、そういった展示がありましたよね?
塚田そうなんです。「死後、自然の一部になりたいですか?」という問いに対して、やっぱり半数以上の人が「なりたい」と答えていたんですよね。樹木葬のニーズが高まっているのも、21世紀を生きる感覚に馴染んでいるんじゃないかなって思いますね。

 END展の展示風景
END展の展示風景
宮嶋確かに、樹木葬を希望されるほとんどの方が「自然の一部になりたい」というイメージをお持ちですね。ただ、樹木葬の正確な定義はなくて、皆さんがイメージされているような、木の下で眠れる商品を実現できている会社さんは少ないんじゃないかなと思います。
かつての沖縄には、遺体を自然の中に安置して吹きさらしにすることで弔う「風葬」と呼ばれる文化がありましたが、現在の日本の法律では難しいでしょうね。
塚田日本も火葬がスタンダードになってから随分と経ちますし、そもそも土葬が禁止されている場所がほとんどなので、そうした土地を見つけるのが難しいという問題はよく聞くんですけど。


塚田アメリカでは微生物に遺体を分解させて、すごく速いスピードで土に還す技術を使った「たい肥葬」のスタートアップが一部で大人気になっているそうです。
アメリカはもともと土葬文化なので根づきやすいこともあるんでしょうけど、日本でもバイオテクノロジーをお墓に導入できたらおもしろそうですよね。虫や鳥や微生物といったステークホルダーが加わって、生態系の一部になれるようなお墓があったら入りたいなってすごく思います。
宮嶋そうですよね。実は私どもも、ビオトープのお墓がつくれないかなと計画を進めていたところでした。最初は建築の力を借りて、人工的なビオトープをつくるんですけれども、半世紀も経てばそこが「風景」になってくると思うんですよね。
お墓を市街地の近くに設置することについて行政からなかなか承認を得られなくて苦戦しているのですが、実現できたらいいなと思っています。
オンライン葬儀では感情の共有ができない


宮嶋先ほどバイオテクノロジーの話が出ましたが、これからはバーチャルテクノロジー葬も進んでいきそうですよね。
塚田オンラインライブ葬はすでに行われていますよね。つい先日、タイに住んでいた日本人の知人が亡くなったのですが、親族の方がタイのお葬式をFacebookライブで中継していて、「あ、こういう時代なのか」と思ったんですよね。
タイのお葬式自体を見るのが初めてで、文化的には興味深かったです。ただ、定点カメラの映像を眺めるだけで感情が動くかと言われると難しいですし、逆に切り離された感じもしてしまいました。
宮嶋やはり同じ場を共有しないと、感情の共有も難しいのでしょうか。
塚田そうですね。ある納棺師の方が「お葬式は感情が連鎖する場所」だと言っていて、Zoom葬儀でも参加したことにはなるかもしれないけど、まさに感情の共有ができないと、残された人はすごく苦しいんじゃないかと話していました。
一方で、能動的なアクションを取り入れれば、そうした問題も少しは解消されるんじゃないのかなと個人的には考えています。お葬式って「何を着ていこう」から始まって、お香典袋を買ったり、お焼香したりと、いろいろな行動をするじゃないですか。
先日のFacebookライブ葬も何かしらの行動できる場が用意されていたら、その人にもう少し寄り添えた機会になったのかなと。実際にやってみないと、わからないですけどね。
葬儀はフィジカルとバーチャルの2極化が進む


宮嶋塚田さんとしては、これからの葬儀はどういった方向に進んでいくと思われますか?
塚田あくまで直観なんですが、メタバースに墓場をつくるといった方向には進んでいかない気がするんですよね。ただ、場合によってはバーチャル葬儀が強く求められるシーンもあると思います。
たとえば、今もしも世界的アイドルのメンバーの誰かが亡くなったら、世界中から寄付が集まって、巨大なメタバース空間がつくられると思うんですよ。つまり、アイコン的な存在の死が、土地に縛られないインターネット空間で弔われていくといったことはすぐにでも起きるんじゃないかなと思います。


塚田ただ、身近な人の死に関しては、お墓がある場所の土を踏みしめるとか、一緒に墓参りに行った友人と酒を飲むとか、そうした自分の身体感覚に直結するような弔い方がますます求められるんじゃないかと。
身近な人はよりフィジカルに、そうでない人はよりバーチャルに。その二極化が進んでいくんじゃないかなと個人的には考えています。
宮嶋そういった意味でも、やはり手を合わせる習慣や文化が大切にされてくるかもしれないですね。最初のお話に戻りますが、「END展」という場が求められたのも、フィジカルな感覚の欠如感ゆえだったのかなという気もしてきます。
塚田そうですね。そうした流れの中心にいるのが10~20代の若い方だということも、「これからの死」という文脈を考えるうえで、非常にポジティブだなと感じています。


宮嶋先ほども少しお話しましたが、私どももこれまで偲ぶことの真ん中と向き合って、等身大のご供養の選択肢となるような装置をつくってきましたので、塚田さんのお考えやご活動に非常に共感します。
ご供養が習慣になった先には、心の豊かさがあるように思います。ご自身の祈りの輪郭を知り、ふさわしい供養の手法を選び、それが日常的な習慣として根付くことで、喪失感の自助となる。祈る習慣は、ご自身が生きるための拠り所にもなるはずです。そうして心の拠り所が生まれることで、精神的な豊かさがもたらされることを願っています。だからこそ私たちは、その習慣の選択肢を作り、そばにいる会社でありたい。
そうした想いで立ち上げたのが、「ありのままに祈る」をコンセプトにしたメディア「素祈(そき)」でした。塚田さんの活動に触れて、「死」について考えることが、大切な人を想う時間をつくるきっかけになるのかもしれないと感じましたので、今日のお話も大変勉強になりました。
Profile
-

塚田 有那(つかだ ありな)
編集者/キュレーター。2021年11月に「死」からテクノロジーと社会の未来を問う展覧会「END展 死×テクノロジー×未来=?」を企画。2022年5月には、二度目となる参加型展覧会「END展 死から問うあなたの人生の物語」を開催した。一般社団法人Whole Universe代表理事。アートサイエンスメディア「Bound Baw」編集長。編著書に『RE-END 死から問うテクノロジーと社会』がある。遠野巡灯篭木(メグリトロゲ)主催