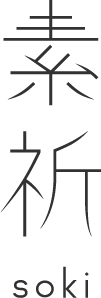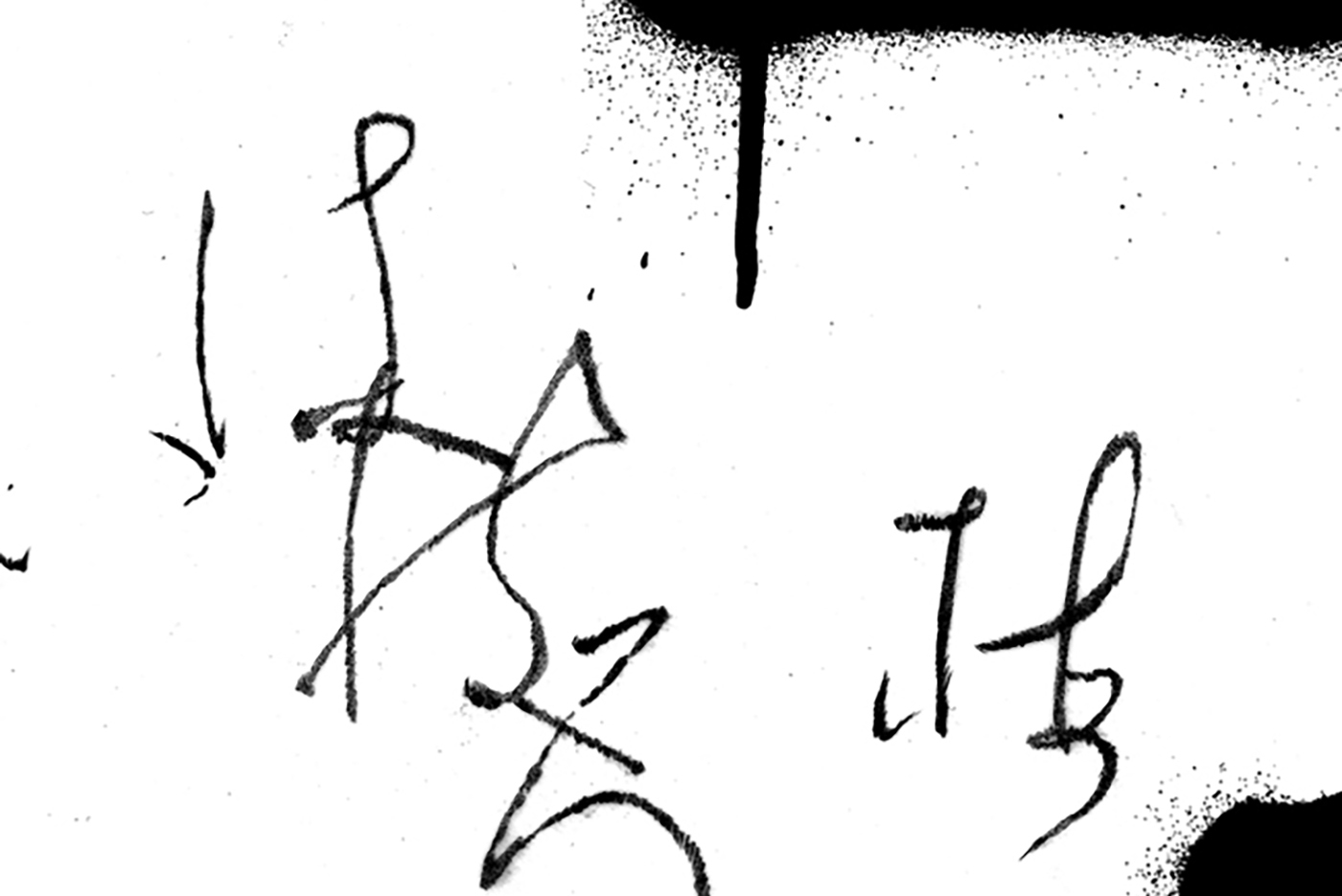
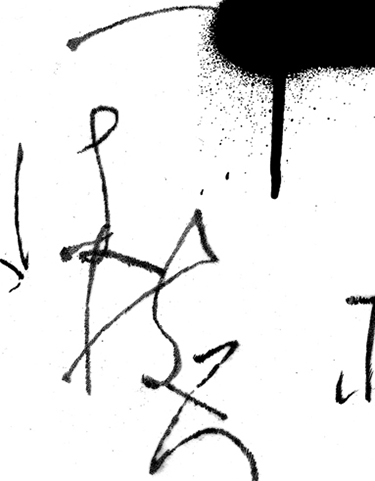
偲ぶことを考える
形見とて 何か残さん 春は花
Essay
2022.9.9 Illustration:Makoto Motomura
古来より人は、死者を弔い偲んできた。それは国境問わず、それぞれの風土や民度をベースとし、様々な手法で定着し受け継がれている。なぜ人は、偲ぶのだろうか。なぜ人は、死者を想うのだろうか。今連載では、そんな人類独自の根源的な営みを、様々な実例や解釈を元に紐解いていきたい。
「死ぬって、
いったいどういうことなの?」
幼いころに、周囲の大人たちに
何度も同じ質問をしたことを
憶えている。
どの人に尋ねてみても、「死」とは
身体や意識がこの世から
消えてなくなることだ、
といわれた。
しかしわたしには、
この世から消えてなくなることが
「死」なのだ、
ということがいまだにうまく
想像できていない。
年端もいかない子に、
突然大きな難問を突きつけられた
大人たちは、さぞかし
面喰らったのではないかと思う。
そもそもわたしたちは
「死」について、
普段から考えることが
あまりないままに過ごしている。
死別などの経験から、
「死」について考える
というよりも、
実は死別と自身の感情との
折り合いをつけることを
「死」を受け止めることとして
了解してきたのではないか。


「死」を考え続けることは、
同時に「生」を
イメージすることで、
二つは対であり、
わたしには切り離して考え、
イメージすることが
どうしてもできない。
唐突なのだけれど、
「お前がいなくなっても、
世の中は動きつづける
(世界は変わらない)」
と教師にいわれたことがある。
「お前がいなくなっても」の
あとに続く言葉が
「世の中は動きつづける」なのか、
「世界は変わらない」なのか
いまではごっちゃになって
判然としないけれど、
とにかくわたしは
「生」と「死」を
イメージするときに
この教師の言葉をいつも思い出す。
教師はおそらく、
わたしの怠慢な態度に
反省を促しながら
この言葉を投げかけたのだろう。
そのときの具体的な
シチュエーションは
よく憶えていないが、
この言葉を投げかけられたとき、
それまでモヤモヤとしていた
「生」へのイメージが
立体的になったことを
鮮明に憶えている。
これほど「生」と「死」を考える
きっかけを与えられた言葉は、
これまで出会ったことがない。


立体的になった
「生」へのイメージとは、
この「生」は偶然にもこのわたしに
降ってきて、この身体で
自由に生きてもよいというような
モヤがかったものではなく、
わたしに与えられたこの「生」は
とりあえず有限なのだから、
日常の中の具体性の積み重ねで
わたしの「生」が
彩られ形作られる、
ということがイメージできるように
なったということだ。
この世に生を受けたのだから、
わたしのこの「生」の
証というものを遺そう、
と誰の頭にも一度は
よぎることかもしれない。
でもそれらに
こだわりつづけるかぎり、
人はその幻影に
翻弄され続けるのではないか。
また身体が「死」の訪れとともに、
それを物質としての身体の
到達点として捉えてみれば、
火葬ひとつとってみても、
この大気中に拡がった
身体を構成する
元素は消えることはない……。
このことを端的に表現した
歌がある。
形見とて 何か残さん 春は花
夏ほととぎす 秋はもみぢ葉
現代の言葉に訳せば、
「わたしを形作った身体が、
いずれ春の野に咲く花々や、
ホトトギスなどの野鳥や、紅葉に
姿を変えまた生まれ来るだろう。
あえて形見など残す必要もない」
といった意味になるだろうか。
1968年に小説家・川端康成氏の
ノーベル文学賞授賞式での講演
(「美しい日本の私 その序説」)
でも紹介された有名な歌で、
江戸後期の僧侶で歌人でもある
良寛(1758 ~1831)は
半ば辞世の歌としてこれを詠んだ。
良寛和尚の歌から
醸し出されるものは、
わたしはやがて衰えて
息絶えるので、
わたしたる所以のなにかを
遺さなくてはならない、
という幻影から解き放たれ、ただ
穏やかに生きることを全うする、
という「生」への全面的な肯定感
そのものではないだろうか。
「死ぬって、
いったいどういうことなの?」
今のわたしは、
幼いころのわたしに、
こう伝えてあげたい。
「まず、生と死を双子のようなものだと想像してほしい。
やがて身体は衰え
「死」を迎えるけれど、
あいかわらず世界は
世界のままでいる。
誰もが一度は思い描く
わたしという証を遺そうと
躍起になるだろうけれど、
そういうことには限界がある。
そんなことにこだわっていないで、
日常での具体性の
積み重ねを手がかりに
「生」を彩り
形作っていってほしい」と。